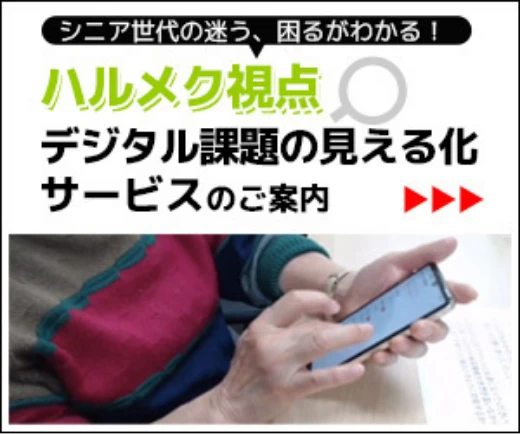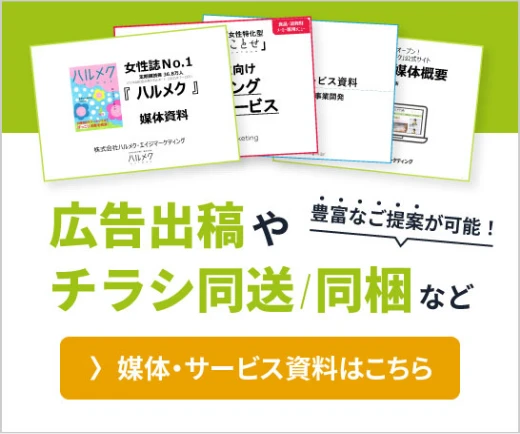骨粗鬆症
骨粗鬆症の意味/解説/説明
骨粗鬆症(こつそしょうしょう)とは、骨密度(単位体積当たりの骨量)が減少し、骨の構造が劣化する進行性の代謝性骨疾患である。
骨粗鬆症になると、骨折しやすくなる。
骨は常に新しい骨が作られ、古い骨が壊されるという「リモデリング」と呼ばれる過程を繰り返している。しかし、骨粗鬆症になると、このリモデリングのバランスが崩れ、骨吸収が骨形成を上回ってしまう状態になる。
骨粗鬆症の原因は、加齢、閉経、遺伝、生活習慣など様々である。
骨粗鬆症の症状としては、腰痛、背中の痛み、身長が縮む、骨折しやすくなるなどがある。
骨粗鬆症の診断は、骨密度検査などでおこなう。骨粗鬆症の治療法としては、薬物療法、運動療法、食事療法などがある。
骨粗鬆症の文字の成り立ち
- 粗:あらい 精白していない米、転じて「あらい」意
- 鬆:あらい。ゆるい。松の葉の重なりから向こうがすけて見えるさまからきている
骨粗鬆症の「粗」も「鬆」も、共に「あらい」という意味で、骨の中の組織が「粗く、スカスカになる」ことから名付けられたといわれている。
骨粗鬆症の歴史
19世紀後半にフランスの医師、ジャン=マルタン・シャルコーが、骨粗鬆症の病名を初めて提唱した。1950年代になると骨密度測定法の開発により、骨粗鬆症の診断が容易になった。
おすすめコラム
 2025-2026年シニアマーケティングトレンドを発表!イマ活・ご自愛消費など5大潮流
2025-2026年シニアマーケティングトレンドを発表!イマ活・ご自愛消費など5大潮流
 令和時代のシニアマーケティングとは?今どきシニアを惹きつけるために必要な4ステップ
令和時代のシニアマーケティングとは?今どきシニアを惹きつけるために必要な4ステップ
 シニア向け雑誌やデジタル媒体は何がある?特徴で比較
シニア向け雑誌やデジタル媒体は何がある?特徴で比較
 「やめる」がシニアを動かす。ハルメク2026年4月号「習慣」特集から読み解く60代の最新インサイト
「やめる」がシニアを動かす。ハルメク2026年4月号「習慣」特集から読み解く60代の最新インサイト
ハルメクグループの
ノウハウやソリューションを提供する
ハルメク・エイジ
マーケティングの
ソリューション



ご相談/お問い合わせ・
資料請求はこちらcontact
(株)ハルメク・エイジマーケティング営業局