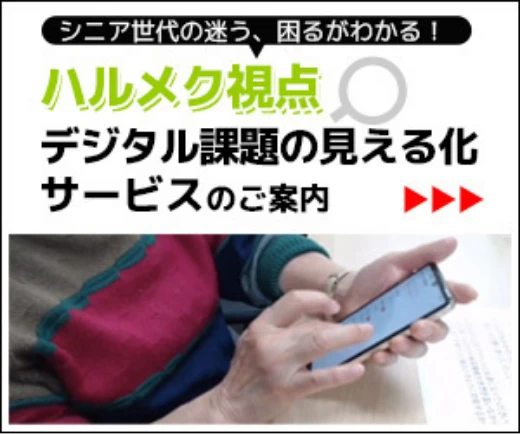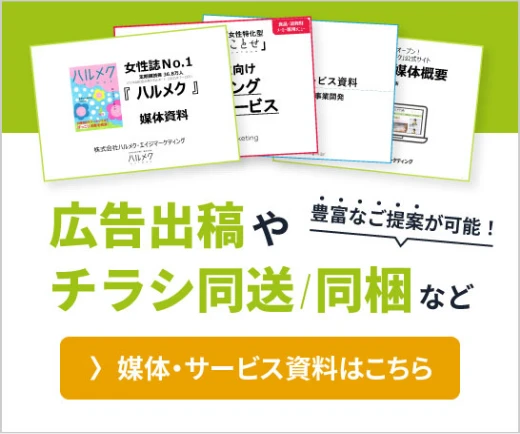グループホーム
グループホーム の意味/解説/説明
グループホームは、認知症高齢者が少人数(5人から9人)で共同生活をする施設である。
グループホームは通称であり、正式名称は「認知症対応型共同生活介護」という。
地域密着型サービスに分類され、一般的に有料老人ホームより費用がかからない。
グループホームの主な特徴は以下の通りである。
- 認知症高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるようにする
- 少人数での共同生活により、家庭的な雰囲気の中で生活できる
- 専門スタッフによる支援を受けながら、自立した生活を目指せる
グループホームに入居するには、65歳以上、要支援2または要介護1以上の認知症患者である必要がある。また、地域密着型サービスであることから、施設と同一地域内の住居と住民票があることが求められる。
グループホーム の歴史
グループホームは18世紀のイギリスで精神病患者向けに提唱されたものが始まりである。その後、1980年代にスウェーデンで認知症高齢者向けに導入され、北欧諸国に広まった。
日本では1989年知的障がい者を対象としたグループホームができたのが最初とされている。
その後1997年には厚生労働省によって「痴呆対応型老人共同生活援助事業」として制度化された。そして2000年に介護保険制度が導入されると、認知症に特化したサービスとして、認知症グループホームが法定され、認知症高齢者のグループホームが広く普及した。
おすすめコラム
 2025-2026年シニアマーケティングトレンドを発表!イマ活・ご自愛消費など5大潮流
2025-2026年シニアマーケティングトレンドを発表!イマ活・ご自愛消費など5大潮流
 令和時代のシニアマーケティングとは?今どきシニアを惹きつけるために必要な4ステップ
令和時代のシニアマーケティングとは?今どきシニアを惹きつけるために必要な4ステップ
 シニア向け雑誌やデジタル媒体は何がある?特徴で比較
シニア向け雑誌やデジタル媒体は何がある?特徴で比較
 「やめる」がシニアを動かす。ハルメク2026年4月号「習慣」特集から読み解く60代の最新インサイト
「やめる」がシニアを動かす。ハルメク2026年4月号「習慣」特集から読み解く60代の最新インサイト
ハルメクグループの
ノウハウやソリューションを提供する
ハルメク・エイジ
マーケティングの
ソリューション



ご相談/お問い合わせ・
資料請求はこちらcontact
(株)ハルメク・エイジマーケティング営業局