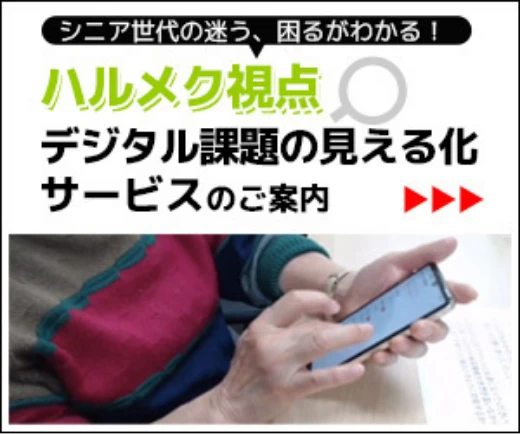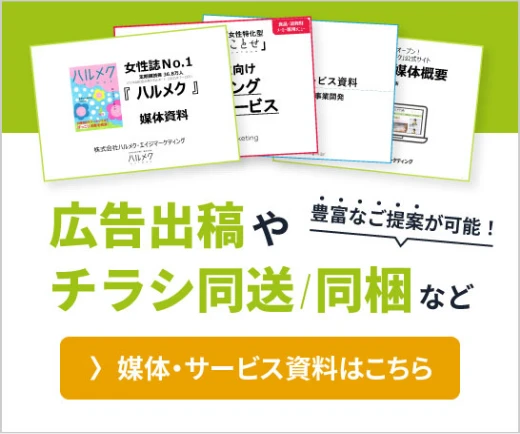ロコモティブシンドローム
ロコモティブシンドローム の意味/解説/説明
ロコモティブシンドローム(ロコモ)とは、運動器の障害によって移動機能が低下した状態をいう。日本語では運動器症候群と呼ばれている。
運動器とは、骨、関節、筋肉、神経など、体を動かすための器官の総称である。これらの器官が衰えると、立ったり歩いたりすることが困難になり、介護が必要になるリスクが高まる。
ロコモは、加齢によって筋力が低下したり、関節や脊椎の病気が発生したり、骨粗鬆症などの骨の病気が進行したりすることで起こる。
ロコモの主な症状は以下の通り。
- 腰痛・膝痛・肩こりなどの痛み
- 歩行速度が遅くなる
- 階段の上り下りが困難になる
- 立ち座りが困難になる
- 転倒しやすくなる
これらの症状が当てはまると、ロコモの可能性がある。
ロコモは、運動習慣とバランスの良い食事によって予防することができる。
運動習慣としては、ウォーキングやスクワットなどの筋力トレーニング、ヨガや太極拳などのバランス運動が効果的である。
バランスの良い食事としては、たんぱく質やカルシウム、ビタミンDなどを積極的に摂取することが大切である。
また、定期的に検診を受け、運動器の障害を早期に発見・治療することも重要である。
ロコモティブシンドローム の歴史
ロコモティブシンドローム(Locomotive Syndrome)という名前は、2007年に日本整形外科学会によって提唱された。
この概念は、高齢者の移動機能の低下を予防し、改善することを目的としており、高齢者が自立した生活を送るための支援を促進するために考案された。ロコモティブシンドロームの「ロコモティブ」という言葉は、「移動する」という意味の「locomotion」から来ている。
おすすめコラム
 「やめる」がシニアを動かす。ハルメク2026年4月号「習慣」特集から読み解く60代の最新インサイト
「やめる」がシニアを動かす。ハルメク2026年4月号「習慣」特集から読み解く60代の最新インサイト
 シニアの最重要関心事「認知症・筋肉」を攻略。『ハルメク』の特集から読み解く60代向けプロモーションとは
シニアの最重要関心事「認知症・筋肉」を攻略。『ハルメク』の特集から読み解く60代向けプロモーションとは
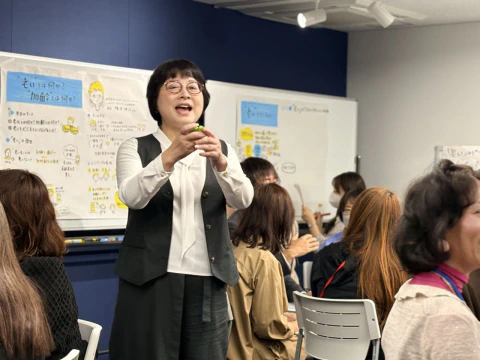 シニアマーケティングの常識が変わる!「老い」を新しい価値に転換する参加型ワークショップ開催レポート
シニアマーケティングの常識が変わる!「老い」を新しい価値に転換する参加型ワークショップ開催レポート
 「パッケージだけでは伝わらない価値」をどう届ける?—永谷園×ハルメク雑誌広告と読者参加イベントの成功事例
「パッケージだけでは伝わらない価値」をどう届ける?—永谷園×ハルメク雑誌広告と読者参加イベントの成功事例
ハルメクグループの
ノウハウやソリューションを提供する
ハルメク・エイジ
マーケティングの
ソリューション



ご相談/お問い合わせ・
資料請求はこちらcontact
(株)ハルメク・エイジマーケティング営業局