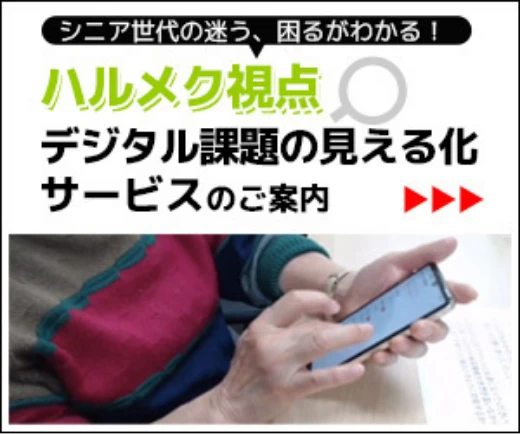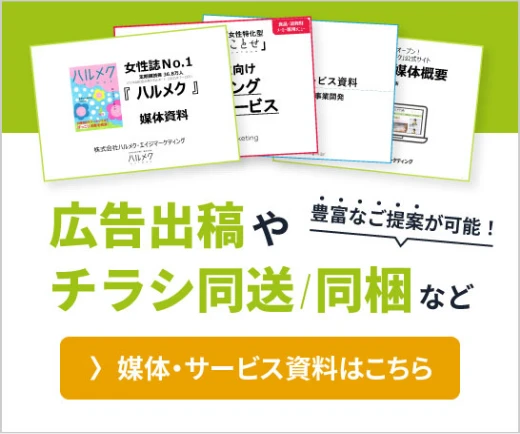福祉車両
福祉車両 の意味/解説/説明
福祉車両は、身体の不自由な人や高齢者など、移動に制約がある人々にとって自由に移動する手段を提供するための特別に設計された車両のことをいう。
福祉車両は、デイサービスの送迎車や介護タクシーとして使用されることが多く、リフト付き車両やスロープ付き車両など、さまざまな種類がある。電動車いすや電動三輪車も福祉車両に分類されることがある。
福祉車両は大きく「介護式」と「自操式」の2種類に分類される。
介護式車両は、身体の不自由な人の介護や送迎に使われるもので、要介護者自身で車両の乗り降りができるよう様々な優しい機能が装備されている。たとえば、助手席回転チルトシートは、座席が車外に向かって回転し、座面と背もたれがチルト(前傾)するため、楽に立ち上がれ、一般の駐車場での乗り降りも可能にしている。
一方、自操式車両は、身体が不自由な人や高齢の人でも自分で運転できるように設計された車両で、手動装置や足動装置など、さまざまな補助装置が付いている。
福祉車両の購入には、消費税の非課税や自動車税の減免など、さまざまな助成制度や優遇制度が設けられており、購入の便宜が図られている。これらの助成制度を活用することで、必要な福祉車両をより手軽に手に入れることが可能となっている。
福祉車両 の歴史
初期段階
日本での福祉車両の開発は、1960年代に遡る。この時期、自動車メーカーは車いすユーザーが自動車に乗り降りしやすいように、特別に設計された車両の提供を開始した。
1972年に町田市といすゞ自動車によって共同開発された「やまゆり号」が、車いすのままで乗れるリフト付きバス第1号として展示されている。
メーカー完成車の登場
1977年に日産は東京モーターショーにキャラバンベースの福祉車両を出展。1980年代に入ると、各自動車メーカーは、福祉車両をメーカー完成車として市場に投入し始めた。1981年に登場したトヨタの「ハンディキャブ」シリーズは、量産車ベースの福祉車両普及の先駆けとなり、福祉車両の認知度向上に大きく貢献した。
技術の進化と普及
1990年代から2000年代にかけて、福祉車両に関する技術は大きく進化し、利便性と安全性、そして利用しやすさが向上した。以降、車両の低価格化とデザインの多様化も進み、より多くの人々が福祉車両を利用できるようになった。
おすすめコラム
 2025-2026年シニアマーケティングトレンドを発表!イマ活・ご自愛消費など5大潮流
2025-2026年シニアマーケティングトレンドを発表!イマ活・ご自愛消費など5大潮流
 令和時代のシニアマーケティングとは?今どきシニアを惹きつけるために必要な4ステップ
令和時代のシニアマーケティングとは?今どきシニアを惹きつけるために必要な4ステップ
 シニア向け雑誌やデジタル媒体は何がある?特徴で比較
シニア向け雑誌やデジタル媒体は何がある?特徴で比較
 「やめる」がシニアを動かす。ハルメク2026年4月号「習慣」特集から読み解く60代の最新インサイト
「やめる」がシニアを動かす。ハルメク2026年4月号「習慣」特集から読み解く60代の最新インサイト
ハルメクグループの
ノウハウやソリューションを提供する
ハルメク・エイジ
マーケティングの
ソリューション



ご相談/お問い合わせ・
資料請求はこちらcontact
(株)ハルメク・エイジマーケティング営業局