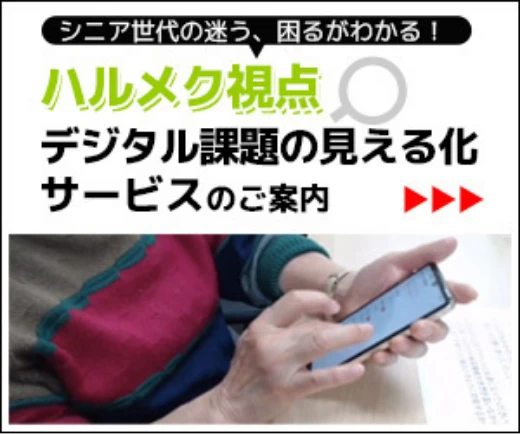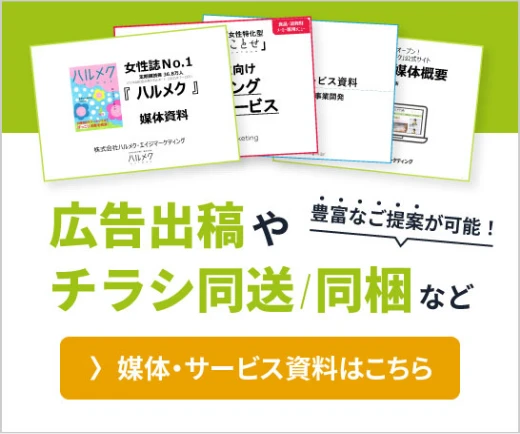高齢者
高齢者 の意味/解説/説明
高齢者とは、年老いた人、年齢が高い人という意味である。
高齢者の定義は時代や地域によって変化しているが、世界保健機関(WHO)では65歳以上を高齢者としている。
日本では、行政上の目的によって異なる定義が用いられている。
例えば、「高齢者の医療の確保に関する法律」では、65歳以上を高齢者とし、そのうち65歳から74歳までの人を前期高齢者、75歳以上の人を後期高齢者と定義している。また「改正道路交通法」では70歳以上を高齢者として、高齢者講習の受講や高齢運転者標識の表示を課している。
「高齢者の医療の確保に関する法律」が制定された1982年(昭和57年)には65歳以上の高齢者の割合は10%未満だったが、2022年には29.1%に上昇している。また、この間に平均寿命も延びている。
近年では、高齢者の健康寿命が延びていることから、「高齢者」の定義を75歳以上に引き上げる議論もされている。
高齢者は、様々な身体的・精神的な変化を経験する。身体的には、筋力や骨密度が低下し、視力や聴力が衰える。また、認知機能の低下や慢性疾患のリスクも高まる。精神的には、孤独感や不安感を感じやすくなる。
高齢者 の歴史
「高齢者」という言葉が使われ始めたのは、1960年代。それまでは「老人」という言葉が一般的であった。しかし「老人」という言葉には、否定的なイメージがあるため、尊重する言葉として「高齢者」という言葉が使われるようになったと考えられる。
法令では、1963年に制定された「老人福祉法」で、はじめて「高齢者」という言葉が使用された。その後、1973年に「老人保健法」が改正され、「高齢者保健法」に改名された。
現在では「高齢者」という言葉が公的な文書や報道などで広く使われている。
用語一覧に戻るおすすめコラム
 2025-2026年シニアマーケティングトレンドを発表!イマ活・ご自愛消費など5大潮流
2025-2026年シニアマーケティングトレンドを発表!イマ活・ご自愛消費など5大潮流
 令和時代のシニアマーケティングとは?今どきシニアを惹きつけるために必要な4ステップ
令和時代のシニアマーケティングとは?今どきシニアを惹きつけるために必要な4ステップ
 シニア向け雑誌やデジタル媒体は何がある?特徴で比較
シニア向け雑誌やデジタル媒体は何がある?特徴で比較
 「やめる」がシニアを動かす。ハルメク2026年4月号「習慣」特集から読み解く60代の最新インサイト
「やめる」がシニアを動かす。ハルメク2026年4月号「習慣」特集から読み解く60代の最新インサイト
ハルメクグループの
ノウハウやソリューションを提供する
ハルメク・エイジ
マーケティングの
ソリューション



ご相談/お問い合わせ・
資料請求はこちらcontact
(株)ハルメク・エイジマーケティング営業局